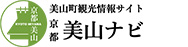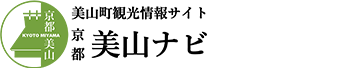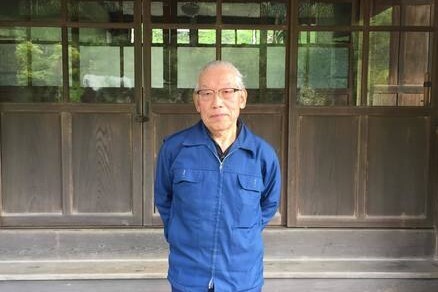美山かやぶきの里の手前、京都府道38号線沿いの内久保地域(南丹市美山町内久保)では毎年ベニバナヤマシャクヤクの鑑賞会が春と秋に行われます(鑑賞会の日程以外は立ち入り禁止となっています)。野草とは思えない見事な花が咲き、薄い花びらに可憐さを感じます。花の魅力や鑑賞会等のお話を伺ったのは、内久保環境/史跡保存会会長(インタビュー時)、栢下壽さん。たくさんの資料と共に丁寧に説明と案内をしていただきました。
ここに注目!ベニバナヤマシャクヤクの魅力
ベニバナヤマシャクヤクは、京都府レッドデータブック(絶滅のおそれのある野生生物種や緊急に保護を要する地理・地質・自然現象、学術上重要な自然生態系について掲載したデータブック)に載る希少野生生物で、「絶滅寸前種」です。
ピンク色と白色の2色の可憐な3~4cmの一重の花が咲き、開花から3~4日で散り、群生地内で花が見られるのは長くて1週間です。内久保の群生地(約2.5ヘクタール)では約4,500本がピンク色と白色が半々に咲いており、幼い株を含めると約8,000本が自生しています。内久保地域の第一の特徴は、他所では90%以上が白花のところ、ここではピンク色の群生が見られることです。美山町では他にも群生地がありますが、花は白色ばかり。なぜ内久保にだけピンク色が多いかを研究している方もいるそうですが、いまだに理由は解明されていないそうです。10月には5本足のヒトデを裏向けにした様に子房がはじけ、10月~11月にかけて群生地内は一面に牡丹が咲いたように真っ赤な里山に変身します。
ベニバナヤマシャクヤクは、種が発芽するまで2年、発芽してからつぼみが付くまで3~4年、花の色の確認まで5~6年かかるため半数が幼い株となります。幼い株を守るためにシダ類など背が高くなる植物の除去も保存会会員さんの手で行われています。ちなみに、この花には毒性があるため、鹿の食害から逃れて群生することができるのだそうです。
ピンク色と白色の2色の可憐な3~4cmの一重の花が咲き、開花から3~4日で散り、群生地内で花が見られるのは長くて1週間です。内久保の群生地(約2.5ヘクタール)では約4,500本がピンク色と白色が半々に咲いており、幼い株を含めると約8,000本が自生しています。内久保地域の第一の特徴は、他所では90%以上が白花のところ、ここではピンク色の群生が見られることです。美山町では他にも群生地がありますが、花は白色ばかり。なぜ内久保にだけピンク色が多いかを研究している方もいるそうですが、いまだに理由は解明されていないそうです。10月には5本足のヒトデを裏向けにした様に子房がはじけ、10月~11月にかけて群生地内は一面に牡丹が咲いたように真っ赤な里山に変身します。
ベニバナヤマシャクヤクは、種が発芽するまで2年、発芽してからつぼみが付くまで3~4年、花の色の確認まで5~6年かかるため半数が幼い株となります。幼い株を守るためにシダ類など背が高くなる植物の除去も保存会会員さんの手で行われています。ちなみに、この花には毒性があるため、鹿の食害から逃れて群生することができるのだそうです。
春と秋に鑑賞会を開催
通常は山の中腹まで登らないと鑑賞できないベニバナヤマシャクヤクですが、内久保地区の鑑賞会は公民館からすぐ近くの里山で鑑賞すること可能なので、特別な装備無しで気軽に参加できます。サイクリングの途中で休憩を兼ねた鑑賞や、京都市内から1時間ほどのドライブや日帰り観光も可能です。
鑑賞会では、ポイントごとにガイドブックを持った保存会の会員メンバーが案内してくれます。10時の集合もしくは希望者がいれば、ガイドをして下さるそうです。受付後は出入り自由。春の散策では山菜の天ぷら、蓮如米のおにぎり、地元野菜の販売があり、その場で春の味覚を楽しむこともできますよ!遊歩道が整備されているので歩きやすく、車イスの方でもゲート付近に車を止めて特定の区域だけですが、鑑賞を楽しむことが可能です。
鑑賞会では、ポイントごとにガイドブックを持った保存会の会員メンバーが案内してくれます。10時の集合もしくは希望者がいれば、ガイドをして下さるそうです。受付後は出入り自由。春の散策では山菜の天ぷら、蓮如米のおにぎり、地元野菜の販売があり、その場で春の味覚を楽しむこともできますよ!遊歩道が整備されているので歩きやすく、車イスの方でもゲート付近に車を止めて特定の区域だけですが、鑑賞を楽しむことが可能です。
興味津々!ベニバナヤマシャクヤクの里を歩く
群生地内を栢下さんの案内で歩きました。遊歩道が整備され、同志社大学の光田重幸先生から保全と増殖のための指導を受けて間伐事業を行い、採光がとられているため、おもったより明るく感じました(3,800ルクスーを10,000ルクスーまで上げた)。雪の後に落ちた杉の枝や葉は会員の方々により綺麗に掃除がされており、悠々と美しい景色が楽しめます。マニアによる不法採取から守るために盗掘防止柵も設置されており、保存会の皆さんのベニバナヤマシャクヤクに対する愛情を深く感じました。
貴重なベニバナヤマシャクヤクの群生を見る感動を是非とも体感してくださいね。
貴重なベニバナヤマシャクヤクの群生を見る感動を是非とも体感してくださいね。